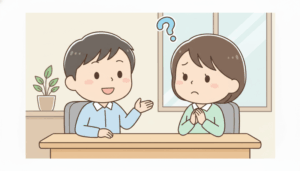内縁の夫の相続、財産はもらえない?諦めないで!今からできる生前対策と死後の手続きを徹底解説
 「長年連れ添ったパートナーが亡くなったら、この先の私の生活はどうなってしまうのだろう?」
「長年連れ添ったパートナーが亡くなったら、この先の私の生活はどうなってしまうのだろう?」
婚姻届は出していないけれど、夫婦同然に暮らしてきたあなたにとって、その不安は計り知れないものでしょう。
残念ながら、日本の法律では、内縁の妻(事実婚のパートナー)には原則として遺産を相続する権利が認められていません。
しかし、だからといって全てを諦める必要はまったくありません。
この記事では、法的な相続権がないという厳しい現実を踏まえつつ、あなたの大切なパートナーの財産を受け取り、安心してこれからの生活を送るための具体的な方法を網羅的に解説します。
パートナーが元気なうちにできることから、万が一の後に取るべき手続きまで、専門知識がなくても理解できるよう分かりやすく説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
【結論】内縁の夫に相続権はない。まず知るべき法律の原則
まず最も重要なことからお伝えします。
現在の日本の法律(民法)では、婚姻届を提出していない内縁の妻や夫には、残念ながらパートナーの財産を相続する権利(法定相続権)が認められていません。
これは、法律が「相続人」となれる人の範囲を、戸籍上の関係に基づいて厳密に定めているためです。
たとえ何十年連れ添い、周囲が認める夫婦関係であったとしても、戸籍上の配偶者でなければ法定相続人にはなれないのです。
この原則を理解することが、適切な対策を考えるための第一歩となります。
なぜ相続できない?民法が定める「法定相続人」とは
法律で定められた遺産を相続できる人のことを「法定相続人」と呼びます。
誰が法定相続人になるかは、民法で優先順位がはっきりと決められています。
内縁の妻は、この法定相続人の範囲に含まれていません。
具体的に誰が相続人になるのか、以下の表で確認してみましょう。
| 優先順位 | 法定相続人 | 法定相続分(配偶者がいる場合) |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者(法律上の妻・夫) | – |
| 第1順位 | 子(実子、養子、認知した子) | 1/2 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母) | 1/3 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 1/4 |
このように、亡くなった方に法律上の配偶者がいれば常に相続人となり、それに加えて第1順位から順に相続人が決まっていきます。
例えば、子がいれば、親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
このルールがあるため、内縁の妻が財産を受け取るには、法定相続とは別の方法を考える必要があります。
内縁関係の子供に相続権はある?「認知」が鍵
あなたとパートナーの間に生まれたお子様の相続権についても、非常に重要なポイントがあります。
それは、パートナーである夫がお子様を「認知」しているかどうかです。
認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子について、父親が自分の子であると法的に認める手続きのことです。
認知がされていれば、その子は法律上の親子と認められ、法定相続人として遺産を相続する権利を持ちます。
| 認知の有無 | 相続権 | 法定相続分 |
|---|---|---|
| 認知あり | あり | 法律上の夫婦の間に生まれた子と全く同じ |
| 認知なし | なし | 法律上の親子関係がないため相続できない |
もしパートナーがまだお子様を認知していない場合は、将来のためにも必ず手続きについて話し合っておきましょう。
お子様の正当な権利を守るために、認知は不可欠な手続きです。
内縁の妻が財産を受け取るための生前対策4選【準備が重要】
法定相続権がないと聞いて、目の前が真っ暗になったかもしれません。
しかし、ご安心ください。
パートナーが元気なうちにきちんと準備をしておけば、あなたが財産を受け取る方法は複数あります。
重要なのは、お二人で将来について話し合い、早めに行動を起こすことです。
ここでは、代表的な4つの生前対策について解説します。
- 遺言書で財産を遺す「遺贈」
- 生前に受け取る「生前贈与」
- 生命保険の活用
- 相続人がいない場合の最終手段「特別縁故者」制度
① 遺言書で財産を遺す「遺贈」|注意すべき遺留分
最も確実で一般的な方法が、パートナーに遺言書を作成してもらうことです。
遺言によって相続人以外の人に財産を渡すことを「遺贈(いぞう)」と呼びます。
遺言書に「内縁の妻である〇〇に、自宅不動産と預貯金の全てを遺贈する」と明確に記すことで、あなたは財産を受け取ることができます。
遺言書には主に2つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
| 種類 | 作成方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する。 | 手軽に作成でき、費用もかからない。 | 形式不備で無効になるリスクがある。紛失や改ざんの恐れがある。家庭裁判所の検認が必要。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人に作成してもらう。 | 形式不備の心配がなく、最も確実性が高い。原本が公証役場に保管される。検認が不要。 | 作成に費用と手間がかかる。証人2人が必要。 |
ただし、遺贈には注意点があります。
それは「遺留分(いりゅうぶん)」です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(子や親など)に法律上保障された最低限の遺産の取り分を指します。
もし遺言書の内容が、他の相続人の遺留分を侵害している場合、その相続人から「遺留分侵害額請求」という金銭の支払いを求める訴えを起こされる可能性があります。
② 生前に受け取る「生前贈与」|暦年贈与の活用
パートナーが生きているうちに、財産を贈与してもらう方法です。
これを「生前贈与」と呼びます。
生前贈与は、年間110万円までであれば贈与税がかからない「暦年贈与」という制度を活用するのが一般的です。
毎年コツコツと非課税の範囲内で贈与を受ければ、将来の生活資金を着実に準備できます。
ただし、いくつか注意点もあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| – 確実に財産を受け取れる | – 年間110万円を超えると高額な贈与税がかかる |
| – 将来の相続財産を減らし、相続税対策になる | – 相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されてしまう |
| – 受け取った財産をすぐに生活に使える | – 不動産を贈与されると、不動産取得税や登録免許税がかかる |
生前贈与も、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。
多額の贈与を行う場合は、遺留分にも配慮した計画が必要です。
③ 生命保険の活用|受取人固有の財産として確保
パートナーに生命保険に加入してもらい、その死亡保険金の受取人にあなたを指定してもらう方法も非常に有効です。
死亡保険金は、原則として相続財産とはみなされず、受取人であるあなたの「固有の財産」となります。
この方法の最大のメリットは、遺産分割協議の対象にならず、他の相続人の遺留分の計算にも含まれない点です。
つまり、他の相続人とのトラブルを避けながら、まとまった生活資金を確実に確保できる可能性が高いのです。
ただし、注意点として、受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
また、法定相続人ではないあなたが受け取る場合、相続税が2割加算されるというルールがあることも覚えておきましょう。
④ 相続人がいない場合の最終手段「特別縁故者」制度
もしパートナーに、子や親、兄弟姉妹といった法定相続人が一人もいない場合、あなたが家庭裁判所に申し立てることで財産を受け取れる可能性があります。
これを「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」に対する財産分与の制度といいます。
この制度を利用するには、厳しい要件を満たし、複雑な手続きを経る必要があります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 主な要件 | – 亡くなった方に法定相続人がいないこと(全員が相続放棄した場合も含む)。 – あなたが亡くなった方と生計を同じくしていた、療養看護に努めたなど、特別な縁故があったこと。 |
| 手続きの流れ | 1. 家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる。 2. 相続財産管理人が相続人を捜索する公告を行う。 3. 相続人が現れなかった場合、公告期間満了後3ヶ月以内に家庭裁判所に財産分与の申立てを行う。 |
| 注意点 | – 手続きに時間がかかり、必ず認められるとは限らない。 – 裁判所が、関係性や貢献度に応じて分与する財産額を決定する。 |
この方法は、あくまで他に相続人がいない場合の例外的な救済措置です。
法定相続人がいる場合は利用できないため、やはり遺言書などの生前対策が基本となります。
相続後の生活を守る重要知識|住まい・税金・年金
無事に財産を受け取る目途が立ったとしても、相続後の生活にはまだ不安が残るかもしれません。
特に「今住んでいる家から出ていかなくてはいけないの?」「税金はどのくらいかかるの?」といった疑問は切実です。
ここでは、あなたの新しい生活の基盤となる「住まい」「税金」「年金」という3つのテーマについて、必ず知っておきたい知識を解説します。
今の家に住み続けたい!居住権の問題と対処法
パートナーが亡くなった後も、思い出の詰まった今の家に住み続けたいと願うのは当然のことです。
しかし、その家がパートナー名義だった場合、家の所有権は法定相続人に移ってしまいます。
法律上の配偶者には、遺産分割が終わるまで無償で自宅に住み続けられる「配偶者居住権」という権利が認められていますが、残念ながら内縁の妻にはこの権利が適用されません。
では、どうすればよいのでしょうか。
過去の判例では、すぐに退去を求めることは「権利の濫用」であるとして、内縁の妻の居住権を事実上保護したケースがあります。
また、家賃を払わずに住んでいた関係を「使用貸借契約」があったとみなし、相続人との間で改めて賃貸借契約を結ぶといった交渉の余地もあります。
ただし、これらは法的な解釈が複雑で、相続人との交渉も必要になります。
不動産が絡む問題はトラブルになりやすいため、必ず弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続税は2割加算に!使えない特例と遺族年金も解説
内縁の妻が遺贈や生命保険で財産を受け取った場合、相続税が課せられます。
その際、法律上の配偶者と比べて税金面で不利になる点がいくつかあります。
| 内縁の妻が直面する税金面のデメリット | 内容 |
|---|---|
| 相続税の2割加сан | 法定相続人ではないため、納税額が2割増しになる。 |
| 配偶者控除が使えない | 1億6,000万円までの財産取得が非課税になる特例が適用されない。 |
| 小規模宅地等の特例が使えない | 自宅の土地の評価額を最大80%減額できる特例が適用されない。 |
| 生命保険金の非課税枠が使えない | 「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用されない。 |
このように、税負担が重くなる可能性があることを理解しておく必要があります。
一方で、生活の支えとなる公的制度もあります。
それが「遺族年金」です。
パートナーが国民年金や厚生年金に加入しており、一定の要件を満たせば、内縁の妻でも遺族年金を受け取ることができます。
生計を維持されていたことなどを証明する必要があるため、詳しくは年金事務所に確認してみましょう。
ひとりで悩まず専門家へ相談を|最適な相談先の選び方と窓口
ここまで様々な方法や制度を解説してきましたが、内縁関係の相続は法律や税金が複雑に絡み合う非常にデリケートな問題です。
ご自身の状況にどの方法が最適なのか、一人で判断するのは難しいかもしれません。
そんな時は、ひとりで抱え込まずに専門家の力を借りることが、トラブルを避け、あなたの権利を守るための最善策です[3]。
相談内容によって、頼るべき専門家が異なります。
| 相談内容 | おすすめの専門家 | 主な業務内容 |
|---|---|---|
| – 遺言書の作成を依頼したい – 相続人とトラブルになりそう |
弁護士 | – 法的に有効な遺言書の作成支援 – 遺留分に関するアドバイス – 相続人との交渉・調停・訴訟の代理 |
| – 相続税や贈与税の計算が不安 – 税務申告をお願いしたい |
税理士 | – 相続税・贈与税のシミュレーション – 節税対策のアドバイス – 税務申告書の作成・提出代行 |
| – 不動産の名義変更をしたい | 司法書士 | – 遺言書や贈与契約書に基づく不動産登記 – 相続登記の手続き代行 |
どこに相談すればよいか分からない場合は、まずはお住まいの自治体や以下の公的機関の無料相談を利用してみるのも良いでしょう。
- 法テラス(日本司法支援センター): 経済的な理由で専門家への相談が難しい場合に、無料法律相談や費用の立替えを行っています。https://www.houterasu.or.jp
- 日本弁護士連合会: 全国の弁護士会の連絡先を検索できます。https://www.nichibenren.or.jp
- 日本税理士会連合会: 全国の税理士会の連絡先を検索できます。https://www.nichizeiren.or.jp
特に、パートナーの財産に不動産が含まれる場合は、その地域の不動産事情に詳しい専門家への相談が不可欠です。
私たちイエステーションのような地域密着型の不動産会社は、地域の相場や特性を熟知しており、不動産の価値を正しく評価し、最適な活用法をご提案できます。相続した不動産の売却をお考えの際も、ぜひお気軽にご相談ください。