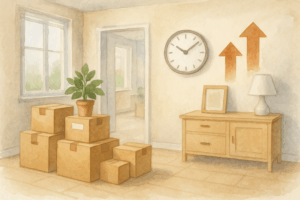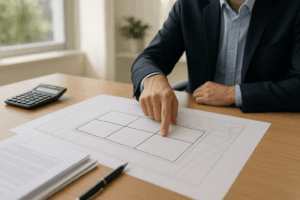【個人向け】土地の分筆売却は違法?安全に進める全手順と税金対策をプロが解説
親から相続した広い土地の固定資産税が、年々大きな負担になっていませんか。
あるいは、ご自身の自宅敷地の一部を売却して、老後の資金や子どもの教育費に充てたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
そのようなお悩みを解決する有効な手段が、土地を法的に分割して一部を売却する「分筆売却」です。
しかし、多くの方が「個人が土地を分割して売ると、法律違反になるのでは?」という大きな不安を抱えています。
ご安心ください。
この記事を最後まで読めば、宅地建物取引業法などの法的なリスクを正しく理解し、費用や税金で損をすることなく、安全に土地を現金化するための知識がすべて身につきます。
複雑な手続きも、専門家と協力しながら着実に進めるための羅針盤となるはずです。

そもそも土地の「分筆売却」とは?基本とメリット・デメリット
まず、「分筆(ぶんぴつ)」という言葉に馴染みがない方も多いかもしれません。
分筆とは、登記簿上で1つの土地(一筆:いっぴつ)を、複数に分割して登記し直す手続きのことです。
人間でいえば、1つの戸籍を法的に分けるようなイメージです。
これにより、例えば100坪の土地を「60坪の自宅用の土地」と「40坪の売却用の土地」に分けることが可能になります。
分筆売却には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 資金計画 | – 土地全体を売らずに必要な分だけ現金化できる – 売却価格を抑えられるため買い手が見つかりやすい |
– 測量や登記に費用がかかる – 残した土地の固定資産税評価額が変わることがある |
| 土地活用 | – 残した土地に家を建てたり、駐車場にしたりできる – 不整形な土地を整形地に分けて価値を高められる可能性がある |
– 分け方によっては土地の価値が下がる(接道義務違反など) – 全体を売却するより、坪単価が下がる可能性がある |
| 相続 | – 相続人間で土地を現物分割しやすくなる – 「売却して現金で分ける」という選択肢が生まれ、トラブルを避けやすい |
– 共有名義の場合、分筆には全員の同意が必要で、手続きが難航することがある |
ご自身の状況が分筆売却に適しているか、まずはこれらの点を踏まえて検討してみましょう。
【一番の不安を解消】個人の分筆売却が宅建業法違反になるケースとは?
多くの方が心配されるのが、宅地建物取引業法(宅建業法)への抵触です。
宅建業法は、不動産取引の専門知識がない消費者を保護するための法律で、事業として不動産取引を行う場合は免許が必要です 。
「個人が自分の土地を売るだけなのに、なぜ事業と見なされるの?」と疑問に思うかもしれません。
それは、売却のやり方によっては「事業性がある」と判断されてしまう可能性があるからです。
どのような場合に事業と見なされるのか、その基準を見ていきましょう。
事業性とみなされる「反復継続」の判断基準
宅建業法違反となるかの大きな分かれ目が、「反復継続」して取引を行ったかどうかです。
「反筆継続」は誤字で、正しくは「反復継続」です。これは、事業として繰り返し土地建物の取引を行っていると見なされる行為を指します。
明確に「何回までならOK」という基準はなく、以下の要素から総合的に判断されます。
- 取引の回数・期間: 短期間に何度も売買を繰り返している
- 取引の対象者: 不特定多数の人に広く購入を呼びかけている
- 取引の目的: 明確に利益を得ることを目的としている
- 取引の態様: 自らチラシを作成したり、広告を出したりして販売活動を行っている
| 項目 | 事業性が高い(宅建業法違反の可能性あり) | 事業性が低い(個人の取引として認められる) |
|---|---|---|
| 目的 | 転売による利益目的 | 相続した土地の整理、資金造成など |
| 回数 | 複数の土地を、複数回に分けて売却 | 1つの土地を分筆し、その一部を1回だけ売却 |
| 相手方 | 不特定多数(広告などで広く募集) | 特定の1人(親族、隣人など) |
| 主体 | 自ら買主を探し、積極的に販売活動を行う | 不動産会社に仲介を依頼する |
このように、単純な回数だけでなく、その背景や目的が重要視されます。
宅建業法に違反せず、合法的に売却するための条件
それでは、どうすれば合法的に売却できるのでしょうか。
結論から言うと、相続や資金化といった個人的な事情で、ご自身の土地を1〜2回程度売却するケースでは、まず宅建業法違反を心配する必要はありません。
特に、以下のような条件を満たしていれば安全です。
- 売却の目的が事業(転売など)ではないこと: あくまで相続資産の整理や、マイホームの資金造成などが目的である。
- 売却は1回限りであること: 1つの土地を2つに分筆し、そのうちの1つだけを売却する。
- 売却活動は不動産会社に任せること: 自ら買主を探したり広告を出したりせず、専門の不動産会社に仲介を依頼する。
複数の土地を売却したい場合は、不動産会社にまとめて買い取ってもらうなど、専門家と相談しながら進めることで、法的なリスクを回避できます。
【5ステップで完了】土地の分筆から売却(現金化)までの全手順
分筆売却の全体像を把握するために、手続きの流れを5つのステップにまとめました。
専門家への依頼から現金化まで、一般的には3ヶ月〜半年、場合によっては1年以上かかることもあります。
| ステップ | 内容 | 主な専門家 | 期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | 測量・境界確定 | 土地家屋調査士 | 1〜3ヶ月 |
| 2 | 分筆登記 | 土地家屋調査士 | 2週間〜1ヶ月 |
| 3 | 不動産会社へ査定・仲介依頼 | 不動産会社 | 1週間〜1ヶ月 |
| 4 | 売却活動・売買契約 | 不動産会社 | 1〜3ヶ月 |
| 5 | 決済・引渡し・所有権移転登記 | 司法書士、不動産会社 | 1ヶ月 |
では、各ステップの具体的な内容を詳しく見ていきましょう。
ステップ1〜2:専門家への依頼から分筆登記まで
分筆手続きの最初の、そして最も重要なステップが「測量」と「境界確定」です。
これは土地の正確な面積を測り、隣の土地との境界線を明確にする作業で、国家資格者である「土地家屋調査士」に依頼します 。
特に、親から相続した古い土地などは境界が曖昧なことが多く、隣地の所有者全員に立ち会ってもらい、合意の上で境界標を設置する必要があります。
この境界確定ができないと、分筆登記そのものができず、売却に進むことができません 。
万が一、隣人との間でトラブルになると解決までに長い時間がかかるため、専門家である土地家屋調査士に間に入ってもらうことが不可欠です。
境界が確定したら、測量図面や境界確定の合意書などの必要書類を揃え、法務局に分筆登記を申請します。
この手続きも土地家屋調査士が代行してくれます。
ステップ3〜5:売却活動から決済・引渡しまで
分筆登記が完了し、売却する土地が法的に独立したら、いよいよ売却活動の開始です。
まずは、信頼できる不動産会社を探し、土地の査定と仲介を依頼します。
複数の会社に査定を依頼し、査定価格の根拠や販売戦略を比較検討することが重要です。
不動産会社と媒介契約を結ぶと、その会社がインターネット広告やチラシなどで購入希望者を探してくれます。
購入希望者が見つかったら、価格や引渡しの時期などの条件交渉を行い、合意すれば「売買契約」を締結します。
この際、契約書の内容を十分に確認し、不明な点は必ず質問しましょう。
契約から約1ヶ月後、買主から売買代金の残金を受け取る「決済」と、土地の所有権を買主に移す「引渡し」を行います。
同時に、司法書士に依頼して法務局で「所有権移転登記」の手続きを行い、これですべての手続きが完了し、土地が現金化されます。
土地の分筆・売却にかかる費用は誰が払う?費用の種類と相場一覧
「結局、全部でいくらかかるの?」という費用面は、最も気になるところでしょう。
分筆と売却には様々な費用が発生します。
ここでは、主な費用の種類と相場、そして誰が負担するのが一般的かを一覧表にまとめました。
| 費用の種類 | 内容 | 費用の相場 | 一般的な負担者 |
|---|---|---|---|
| 測量・境界確定費用 | 土地の面積を測り、隣地との境界を確定する費用 | 30万円 〜 100万円以上 | 売主 |
| 土地家屋調査士報酬 | 分筆登記の申請を代行してもらう費用 | 5万円 〜 10万円 | 売主 |
| 登録免許税(分筆) | 分筆登記の際に法務局に納める税金 | 分筆後の土地1筆につき1,000円 | 売主 |
| 不動産仲介手数料 | 売却を仲介してくれた不動産会社に支払う成功報酬 | (売却価格 × 3% + 6万円)+ 消費税(上限) | 売主 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼る印紙代 | 1万円(売却価格が1,000万円超5,000万円以下の場合) | 売主・買主で折半 |
| 登録免許税(所有権移転) | 土地の所有権を買主に移転する登記の税金 | 固定資産税評価額 × 1.5%(軽減税率適用時) | 買主 |
| 司法書士報酬 | 所有権移転登記を代行してもらう費用 | 5万円 〜 10万円 | 買主 |
測量費用は土地の状況によって大きく変動しますが、全体として売主の負担は数十万円から百数十万円になる可能性があります。
事前に不動産会社に見積もりを依頼し、資金計画を立てておくことが重要です。
【知らないと損】土地売却の税金はいくら?計算方法と節税特例を解説
土地の売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」がかかります。
この税金は、売却した翌年に確定申告をして納税する必要があります。
税額を大きく左右するのが、売却した土地の「所有期間」です。
所有期間が5年を超えるかどうかで、税率が約2倍も変わってきます。
| 所有期間 | 区分 | 税率(所得税+復興特別所得税+住民税) |
|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315% |
親から相続した土地の場合は、親がその土地を取得した時期から所有期間を計算できます。
この税金の仕組みを知らないと、大きな損をしてしまう可能性があります。
譲渡所得税の計算シミュレーション
譲渡所得税は、以下の計算式で算出します。
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
- 取得費: その土地を過去に購入したときの代金や手数料など。不明な場合は売却価格の5%で計算できます。
- 譲渡費用: 今回の売却でかかった仲介手数料や測量費など。
それでは、具体的な例でシミュレーションしてみましょう。
【例】
- 売却価格: 4,000万円
- 取得費: 2,000万円
- 譲渡費用: 300万円
- 所有期間: 7年(長期譲渡所得)
譲渡所得: 4,000万円 – (2,000万円 + 300万円) = 1,700万円
譲渡所得税: 1,700万円 × 20.315% = 約345万円
もし所有期間が5年以内(短期)だった場合、税率は39.63%となり、税額は約673万円にもなります。
所有期間を意識することが、いかに重要かお分かりいただけるでしょう。
必ず活用したい節税特例(3,000万円特別控除・取得費加算など)
幸いなことに、税金の負担を大きく軽減できる特例制度が用意されています。
特に重要なのが、以下の2つです。
- マイホームを売ったときの3,000万円特別控除
ご自身が住んでいた家とその敷地の一部を売却する場合に使える強力な特例です。
譲渡所得から最高で3,000万円を控除できます 。
例えば、先のシミュレーションで譲渡所得が1,700万円だった場合、この控除を使えば譲渡所得は0円になり、税金はかからなくなります。 - 相続財産を売ったときの取得費加算の特例
相続で取得した土地を、相続開始から3年10ヶ月以内に売却した場合に使える特例です。
支払った相続税の一部を、土地の取得費に加算することができます 。
取得費が増えることで譲渡所得が圧縮され、結果的に税金が安くなります。
これらの特例が使えるかどうかで、手元に残る金額が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
ご自身の状況が適用対象になるか、必ず税務署や税理士、あるいは詳しい不動産会社に確認しましょう。
売却前に必ず確認!分筆で土地の価値を下げないための法的注意点
分筆は、やり方を間違えると残した土地や売却する土地の価値を大きく下げてしまう危険性があります。
手続きを進める前に、以下の法的な注意点を必ず確認してください。
- 接道義務を満たしているか
建築基準法では、建物を建てる敷地は「幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」と定められています [7]。
分筆によって、この条件を満たさない土地(無道路地)ができてしまうと、その土地には家を建てられなくなり、資産価値が著しく低下してしまいます。 - 最低敷地面積を下回らないか
各自治体では、条例によって建物を建てられる土地の最低面積が定められている場合があります(例:50㎡以上など)。
分筆後の土地がこの面積を下回ると、やはり建物を建てられなくなってしまいます。 - 共有名義の場合は全員の同意があるか
相続した土地などが兄弟などの共有名義になっている場合、分筆や売却を行うには共有者全員の同意が必要です 。
一人でも反対者がいると、手続きを進めることはできません。 - 境界トラブルは解決しているか
隣地との境界線が確定していない、あるいは揉めている状態では、土地を売却することは非常に困難です 。
必ず分筆前に、土地家屋調査士に依頼して境界を確定させる必要があります。
これらのポイントは専門的な知識が必要なため、自己判断は禁物です。
必ず不動産会社や土地家屋調査士に相談しながら、慎重に分筆計画を立てましょう。
複雑な分筆売却はプロに相談が安心!イエステーションが選ばれる理由
ここまでお読みいただき、個人の分筆売却が法律や税金、専門的な手続きが絡む複雑なものであることをご理解いただけたと思います。
これらの手続きを、知識がないままご自身だけで進めるのは非常にリスクが高いと言えるでしょう。
そこで重要になるのが、信頼できる専門家をパートナーに選ぶことです。
イエステーションは、全国に200以上の店舗を展開する不動産売買の専門家集団です。
年間7,000件を超える売買仲介実績があり、多くのお客様から「担当者の対応が丁寧で、地域の情報に詳しかったため安心できた」とのお声をいただいています 。
イエステーションの最大の強みは、全国ネットワークでありながら、各店舗がその地域に特化した「地域専門性」です 。
担当者は担当エリアの都市計画や条例、市場動向を熟知しているため、お客様の土地の価値を最大限に引き出す分筆案や売却戦略をご提案できます。
複雑な分筆売却だからこそ、その土地のことを誰よりも知る「あなたの町の専門家」であるイエステーションに、ぜひ一度ご相談ください。
無料の査定依頼から、お客様の不安や疑問に丁寧にお答えします。
まとめ:土地の分筆売却を成功させるために
この記事では、個人が土地を分筆して売却する際の法律、手順、費用、税金について網羅的に解説しました。
最後に、分筆売却を成功させるための重要なポイントを4つにまとめます。
- 1. 法規制(宅建業法)を正しく理解する
事業目的でなければ、個人の1回限りの分筆売却は基本的に問題ありません。不安な場合は必ず専門家に確認しましょう。 - 2. 手順と費用・税金の全体像を把握する
事前に流れとコストを把握し、余裕を持った資金計画を立てることが重要です。 - 3. 価値を下げない分筆計画を立てる
接道義務や最低敷地面積などの法規制を守り、土地の資産価値を損なわないよう専門家と計画を立てましょう。 - 4. 信頼できる専門家をパートナーに選ぶ
土地家屋調査士、司法書士、そして何より地域に精通した不動産会社選びが成功の鍵を握ります。
固定資産税の負担や将来の資金への不安を、これ以上一人で抱え込む必要はありません。
まずは信頼できる専門家への無料相談から、問題解決への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。