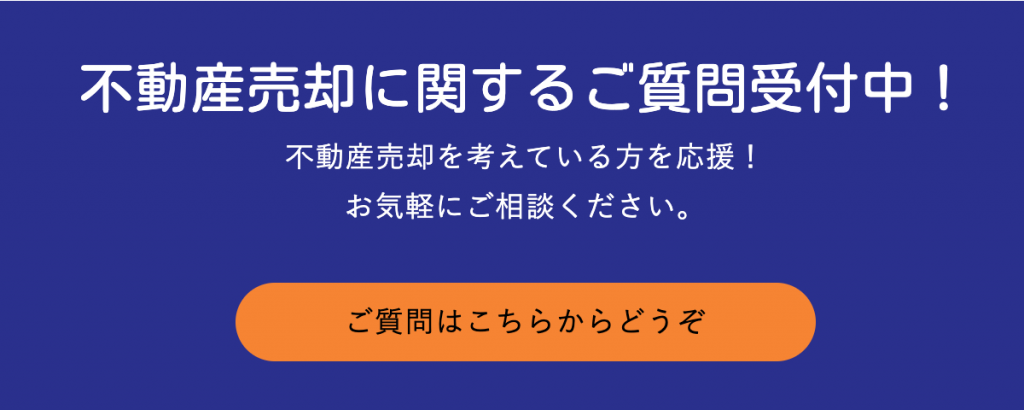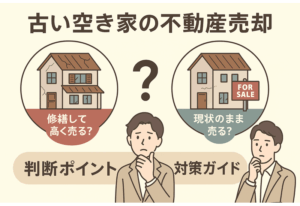未登記物件の売買は可能?リスクと手続きを完全ガイド|安全な取引の秘訣
 「親から相続した実家が、実は未登記だった…」
「親から相続した実家が、実は未登記だった…」
「昔、増改築した部分の登記を忘れていたかもしれない…」
このような状況で、未登記物件の売買を考え始めたとき、多くの疑問や不安が頭をよぎるのではないでしょうか。
そもそも売買できるのか、法的なリスクはないのか、費用は一体いくらかかるのか。
専門的な内容が多く、どこから手をつけていいか分からなくなるのも無理はありません。
ご安心ください。
この記事では、未登記物件の売買に関する疑問を解消します。
売買に伴うリスクから、安全に取引を進めるための具体的な方法、必要な手続きと費用まで、専門知識がない方にも分かりやすく徹底的に解説します。
最後までお読みいただければ、漠然とした不安が晴れ、自信を持って次の一歩を踏み出せるはずです。
そもそも「未登記物件」とは?あなたの家が未登記になった理由
「未登記物件」とは、法務局にある公式な記録帳である「登記簿」に、建物の情報が記載されていない状態の物件を指します。
建物が物理的に存在しているにもかかわらず、その所在や構造、所有者などの情報が公的に登録されていないのです。
不動産の登記には、主に2つの重要な部分があります。
- 表題登記
- 内容:建物の物理的な情報(所在地、構造、床面積など)を記録しま
- 役割:「ここにこういう建物があります」という存在証明の役割を果たします。
- 権利部の登記
- 内容:所有者の住所・氏名などの権利に関する情報を記録します。これには最初の所有者を記録する「所有権保存登記」や、相続による名義変更の「相続登記」などがあります。
- 役割:「この建物の持ち主は誰か」を公的に証明する役割を果たします。
未登記物件は、この「表題登記」がされていないケースや、「表題登記」はあっても「所有権保存登記」がされていないケースなどがあります。
では、なぜ未登記の状態になってしまうのでしょうか。
その理由は様々で、決して珍しいことではありません。
- 歴史的背景や知識不足:過去には登記が義務ではなかった時代もあり、手続きの必要性を知らないまま現在に至るケース。
- 費用の節約:登記には登録免許税や専門家への報酬がかかるため、特に現金で購入した場合などに費用を抑える目的で登記されないケース。
- 相続による未登記:親から不動産を相続した際に、相続登記が行われず未登記のまま引き継がれるケース。
- 増改築部分の未登記:建物を増築・改築した際に、その変更部分の登記(建物表題変更登記)を怠ってしまうケース。
- 建築時の事情:建築基準法に適合しない違法建築の部分があると、登記申請が受理されないため未登記状態になるケース。
ご自身の物件が未登記であることに気づいても、まずは焦らずに現状を把握することが大切です。
【結論】売買は可能!ただし売主・買主双方に大きなリスクが伴う
読者の皆様が最も知りたい結論からお伝えします。
未登記物件の売買は、法律上「可能」です。
しかし、その取引には通常の不動産売買とは比較にならないほど多くのリスクが伴います。
売主・買主それぞれの立場で、どのようなリスクがあるのかを正しく理解しておくことが、トラブルを避けるための第一歩です。
- お金・ローンに関するリスク
- 売主のリスク: 買主が住宅ローンを利用できないため、現金が用意できる買主のみが対象となる。
- 買主のリスク: 住宅ローンを利用できない。
- 対策・注意点: 売主が事前に登記を済ませるか、買主が現金で購入する必要がある。
- 権利に関するリスク
- 売主のリスク: 他の人が自分名義で登記した場合に建物の所有権が奪われてしまう。
- 買主のリスク: 所有権を第三者に主張できない(対抗できない)。[^6]
- 対策・注意点: 登記をしなければ、法的に所有者として認められない。
- 取引上のリスク
- 売主のリスク: 契約後の登記の場合、買主は安心して取引できない。
- 買主のリスク: 売主が別の人にも売却する「二重譲渡」のリスクがある。
- 対策・注意点: 契約書の内容を精査し、専門家のチェックを受けることが不可欠。
特に重要なのが、買主が「所有権を第三者に主張できない」という点です。
日本の民法では、不動産の所有権は登記をもって第三者に対抗できると定められています(民法177条)。
つまり、いくら売買契約を結んで代金を支払っても、登記をしなければ、後から現れた別の買主や売主の債権者に「この家の所有者は私だ」と主張されても対抗できず、最悪の場合、所有権を失ってしまう可能性があるのです。
未登記物件を安全に売買する3つの方法|状況別の最適解とは?
大きなリスクがある未登記物件ですが、安全に売買するための方法は存在します。
ご自身の状況や物件の状態に合わせて、最適な方法を選択することが重要です。
ここでは、代表的な3つの方法をご紹介します。
- 【推奨】売主が登記を済ませてから売却する
- 建物を解体して「更地」として売却する
- 【高リスク】未登記のまま売買する
それぞれの方法について、メリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。
方法1【推奨】:売主が登記を済ませてから売却する
最も安全で、トラブルの可能性が低いのがこの方法です。
売買契約を結ぶ前に、売主の責任と費用で建物の登記を完了させ、通常の不動産と同じ状態にしてから売却します。
- メリット
✔️ 買主が住宅ローンを組めるため、買い手が見つかりやすい。
✔️ 売却価格が相場通りになり、高値で売れる可能性がある。
✔️ 売主・買主ともに取引の安全性が高く、後のトラブルを防げる。
- デメリット
✖️ 登記費用(数十万円)と時間がかかる。
✖️ 専門家(土地家屋調査士・司法書士)への依頼など手間がかかる。
手間と費用はかかりますが、それを補って余りあるメリットがあります。
特に理由がない限り、この方法を選択することを強くお勧めします。
方法2:建物を解体して「更地」として売却する
建物が非常に古い、劣化が激しく資産価値がない、といった場合には有効な選択肢です。
未登記の建物を解体し、土地のみを売却する方法です。
- メリット:
✔️ 建物の欠陥に関する「契約不適合責任」を問われるリスクがなくなる。
✔️ 買い手は自由に新しい建物を建てられるため、土地として売れやすい場合がある。
- デメリット:
✖️ 建物の解体費用(100万円〜)がかかる。
✖️ 更地にすると固定資産税の優遇措置がなくなり、税額が上がる可能性がある。
この方法を選択した場合、建物を解体した後に「建物滅失登記」を申請する義務があることを覚えておきましょう。
方法3【高リスク】:未登記のまま売買する
この方法は、原則として避けるべき選択肢です。
主に、買主が現金一括で購入できる親族間売買や、専門の買取業者に売却する場合などに限られます。
- 売主のデメリット:
- 売却価格が相場より2割〜3割、あるいはそれ以上安くなる。
- 買い手が限定されるため、売却まで時間がかかる可能性がある。
- 契約書に「登記は買主の責任と費用で行う」と明記しないと、後々トラブルになる。
- 買主のデメリット:
- 住宅ローンが利用できない。
- 所有権が法的に不安定な状態が続く。
- 将来、自身が売却したり、相続させたりする際に結局登記が必要になり、手間と費用がかかる。
この方法を選ぶ際は、売買後に固定資産税の納税義務者を変更するため、市町村役場へ「家屋補充課税台帳登録事項変更届」などを提出する必要があります。
【実践】未登記建物を登記する手続きの全手順と費用
「方法1:登記を済ませてから売却する」を選んだ方のために、ここからは具体的な登記手続きについて解説します。
登記手続きは専門的な知識が必要なため、専門家に依頼するのが一般的です。
手続きは、大きく分けて以下の2つのステップで進みます。
建物表題登記:土地家屋調査士に依頼
所有権保存登記:司法書士に依頼
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
STEP1:建物の物理的状況を登録する「建物表題登記」
建物表題登記は、建物の「スペック」を法務局に登録する手続きです。
「どこに、どんな構造で、どれくらいの広さの建物があるのか」を公的に記録します。
この登記は、国家資格者である土地家屋調査士の専門分野です。
- 登記申請書: 土地家屋調査士が作成します。
- 所有権証明書: 建築確認済証、検査済証、工事完了引渡証明書など。
- 住民票: 申請者の現在の住所を証明します。
- 図面類: 建物図面、各階平面図など。土地家屋調査士が測量して作成します。
- 相続関係書類(相続した場合): 戸籍謄本、遺産分割協議書など。
上記の書類が手元にない場合でも、土地家屋調査士に相談すれば、現地調査や測量を通じて書類を作成してもらえることがほとんどです。
STEP2:最初の所有者を登録する「所有権保存登記」
建物表題登記が完了し、登記簿に建物のスペックが記録されたら、次に「誰が最初の所有者か」を登録する所有権保存登記を行います。
この登記によって、初めて第三者に対して正式に所有権を主張できるようになります。
こちらは、法律と登記の専門家である司法書士に依頼します。
- 登記申請書: 司法書士が作成します。
- 住民票: 申請者の住所を証明します。
- 固定資産評価証明書: 市町村役場で取得します。登録免許税の計算に必要です。
- 印鑑証明書・実印: 場合によって必要になります。
もし、建物を相続によって取得した場合は、所有権保存登記の前に「相続登記」が必要になる場合があります。
このあたりは複雑なため、司法書士に状況を説明し、最適な手続きを案内してもらうのが確実です。[^9]
登記にかかる費用と期間の目安
登記にかかる費用は、物件の評価額や依頼する専門家によって変動しますが、おおよその目安は以下の通りです。
- 土地家屋調査士への報酬: 8万円 〜 20万円程度 (建物表題登記の依頼費用です。)
- 司法書士への報酬: 3万円 〜 8万円程度 (所有権保存登記の依頼費用です。)
- 登録免許税: 不動産評価額 × 0.4% (所有権保存登記で法務局に納める税金です。(軽減措置あり))
- その他実費: 数千円 〜 1万円程度 (住民票や印鑑証明書の取得費用、交通費などです。)
合計で、数十万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
手続きにかかる期間は、書類の準備状況や法務局の混雑具合にもよりますが、申請から完了まで数週間から2ヶ月程度が目安となります。
トラブル回避の鍵!売買契約書と重要事項説明のポイント
登記手続きと並行して、売買契約の準備も重要になります。
特に未登記物件の取引では、契約書や重要事項説明の内容が、将来のトラブルを防ぐための生命線となります。
口約束は絶対に避け、すべての合意事項を書面に残すことが鉄則です。
ここまでお読みいただき、未登記物件の売買には専門家のサポートが不可欠であることをご理解いただけたかと思います。
では、具体的に誰に、何を相談すればよいのでしょうか。
- 土地家屋調査士:建物の測量、図面の作成、建物表題登記の申請代理。
- 司法書士:所有権保存登記や相続登記、売買に伴う権利移転登記の申請代理。
- 不動産会社:物件の査定、売却活動、売買契約に関する取引の調整とまとめ役、重要事項説明など。
まずは、信頼できる不動産会社に相談し、全体の流れや売却戦略についてアドバイスをもらうのがスムーズです。
その上で、不動産会社と提携している土地家屋調査士や司法書士を紹介してもらうのが一般的です。
【実績で選ぶ】複雑な未登記物件の売買こそ地域密着型の「イエステーション」へ
未登記物件のような複雑な案件では、マニュアル通りの対応しかできない不動産会社では不安が残ります。
その地域の特性や法規制に精通し、様々なケースに柔軟に対応できる会社を選ぶことが成功の鍵です。
私たちイエステーションは、全国に展開する地域密着型の不動産フランチャイズです。
各店舗がその地域の専門家として、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案をしています。
2024年度のグループ全体の売買仲介契約数は7,693件にのぼり、多くのお客様から高い評価をいただいております。
未登記物件の売買はもちろん、相続対策やリフォームなど、不動産に関するあらゆるお悩みにワンストップで対応できる体制が整っています。
どの専門家に相談すれば良いか分からない場合でも、まずはイエステーションにご相談いただければ、私たちが責任を持って適切な専門家との橋渡しをいたします。